一九七六年、文革派を打倒し以後二〇年余にわたる「改革開放」の道を歩んできた中国と中国共産党は二一世紀を迎えて新たな相貌を示し出している。
それを象徴的に示したのが、昨年一二月の中国共産党第一六回大会において江沢民があらためて述べた「三つの代表」論である。
「わが党は一貫して、中国の先進的な生産力の発展の要求を代表し、中国の先進的な文化の進む方向を代表し、中国の最も広範な人民の利益を代表しなければならない」。
現在、中国共産党は「三つの代表」論の「偉大な意義」について大々的なキャンペーンに入っており、各領域からの模範入党が報じられている。中国は国を挙げて「偉大な中華民族の復興」(江沢民「第一六回大会報告」)への熱気のなかにあるかのごとくである。
この「三つの代表」論はこの間の「改革開放」路線が実現した中国の輝かしい発展を受けて提起されたとされている。そこでは一九八九年の天安門事件と九九年の法輪功事件の総括については口は閉ざされたままである。だが統治党とその周囲のイデオローグたちが描き出す光景とは別の声も同じ中国から聞こえてくる。
資本家層の入党を認めるということは「社会民主党」、「改良主義党」への道だとただちに意見書を提出して抗議した鄧力群ら「党内左派」や「太子党」たちの声もその一つである。また当局によってその発言を封じられアメリカに移住した何清漣はその『現代化の落とし穴』(草思社、2002)において中国の別の現実をリアルに描き出している。
この「社会民主党への変質」論に対して海外民運派の胡平(「中国民主団結聯盟」主席)は、そんなことではないのだと言う。社会民主主義は少なくとも「社会主義」と「民主」を堅持しているのだが、中国共産党のこの間の変化はそういうものではなく、「一つの全体主義党として、その党員の社会的要素にどんな変化があろうともその全体主義的性格に実質的な影響を及ぼすことはありえない」(「中国共産党の資本家入党の許可を評す」)と言うのがその主張である。
「中国共産党は戦車と機関銃によって民主運動を鎮圧し、その後は専制的な鉄腕をもって私有化改革を推し進めてきたことにより、政治的には専制と暴虐を、経済的には腐敗と貪婪を一身に集めた怪物へと変化した」。(「中国共産党は社会民主党に変化しつつあるのか」)
この「三つの代表」論をもって中国はどこへ向おうとしているのかについて北京大学教授の康暁光がきわめて興味ある分析をおこなっている。
それによれば今日中国共産党は「集権主義体制」から「権威主義体制」へと変化してきており、その「社会的基礎」を成しているは「政治エリート」を中核とする「統治集団」と「経済エリートと知識エリート」との「同盟」なのだが、実のところこの「政治エリート」は誰をも「代表」していないのだと言うのである。
「『エリート政治』をもって中国政治の本質とすることはできない。実際のところあらゆる政治はエリート政治である。・・・中国大陸の『特色』は統治の任務をおこなう党と政府の官僚集団そのものがすなわち統治階級であり、統治集団すなわち統治階級、代理人すなわち委託者というところにある。政治エリートはいかなる階級も代表していない。彼らは一切の階級を凌駕しており、すべての階級に『権威主義』的統治をおこなっている。彼らは只々自己の利益に責任を負っているだけである」。(「今後3-5年の中国大陸における政治的安定性の分析」)
「いかなる階級も代表していない」統治集団とは一体何者なのか。そしてこれら「統治集団」の実態について康暁光はさらに驚くべきことを述べている。
「元々のイデオロギーは破産したのだが、新たなイデオロギーはまだ生み出されていない。今日の共産党について言えばマルクス主義、レーニン主義、毛沢東思想はただその正当性を粉飾するものでしかなく、恥部を隠す役に立たないベールでしかない。その手中にある精神的資源としては『鄧小平理論』すなわち『実用主義』があるだけである」。
「イデオロギーの終焉は一連の重大な結果をもたらした。その一は中国共産党が『革命党』から『執政党』へと変貌したことである。現在、中国共産党の組織目標は『資本主義を消滅させる』ことではなく、ただただ『執政』あるいは『統治』である。その二は中国共産党の正真正銘の『理性的経済人』への変化である。大統治集団の既得利益を維持ないし拡大できさえすれば、いかなる理論、進路、原則、価値をも受け入れ可能である。その三は個々の党員、幹部たちに道徳なく、理想なく、人生の意義と帰結を知ることもないことである。絶大多数の党と政府の党員および幹部を生活と仕事に駆り立てているのは、人類の最も原始的な生物学的欲望である」。
「『八九』〔天安門事件〕のあと、中国共産党は政治的反対派の活動と独立した社会組織を情け容赦なく鎮圧した」。 「中国共産党はその極端な専制によって一切の政治的対抗者を消滅させてしまっており、国内で中国共産党に取って代わったり任を引き継ぐ勢力が一つも生まれることがないようにさせた」。
その結果、「中国大陸で最も重要なのは政府の安定性である。政府が打ち倒されたとき、統治者と彼らが奉じる政策、擁護する現行制度もすべて徹底的に葬り去られるかもしれない。そして政府の不安定は全面的な不安定、たとえば経済の崩壊、社会動乱、民族的衝突、分裂、内戦、ないしは国際的衝突を引き起こす可能性がある」。
そして一九六三年生まれのこの康暁光は政治的異論派でもなければ、自由派、「新左派」でもなく一人の体制寄りの学者なのである。
これには批判もある。
「この分析はジラスの『新階級』理論に依拠したものであり、スターリン――チト-――毛沢東の時代の社会的現実には大体符合しているが、目下の社会的現実には不適応である。まさに康暁光論文が述べているように『八〇年代後期、中国大陸では集権主義体制から権威主義体制への転化が完成した』のである。・・・全能主義体制の転型につれて一元化されていた統治エリートは政治エリート、経済エリートと知識エリートに分化し、政治エリートの代表的、『代理人』的性格が顕著になり、少なくとも彼らは自己の同盟軍――経済エリートと知識エリート――を代表することが必要となった。これこそが『三つの代表』の真諦なのである」。(何家棟、王思叡「社会階層の分析と政治的安定の研究」)
だが康暁光の分析が「改良主義党」などでは押さえきれない今日の中国共産党の奇怪な性格を見ていくに際して一つの重要な示唆を与えているのは確かである。
この文章を「『六四』〔天安門事件〕以降の一三年間の中で最も重要なもの」と高く評価する胡平は、しかしそれは「中国共産党の専制擁護の絶唱」なのだと言う。と言うのも、ここまで冷徹に今日の中国共産党政権を分析した康暁光のこの文章の結論はつぎのようなものだったからである。
「自己の根本的利益を維持し守るためには、中国共産党は必ずエリートの利益を適当な限度に制限する必要がある。それはエリート間の連盟の破裂を引き起こし瓦解させる可能性がきわめて高いことから、現在の政治的安定を維持する重要な基礎なのである。すなわち、中国共産党の手中にあるのは『諸刃の刃』なのであり、安定性の問題を力で威嚇して解決しようとすることは往々にして安定性の基礎を破壊することになるからである」。
「見方を変えれば、中国大陸の安定性は中国共産党の理性と民衆の忍耐力によって決まるのである。もし中国共産党が理性を備えており、問題を終始大衆が容認できる範囲内に制限することができるなら政治的安定の維持は可能である」。 ここでの「適当な限度に制限する」という言い方に注目しつつ胡平は康暁光論文が「専制擁護の絶唱」ある所以をこうまとめている。
「ますます厳重となる社会的不満に直面して康暁光たちが政府に提出した建議のすべてはつぎの一言に帰結する。すなわち『われわれは節度をもって彼らを搾取しようではないか』」。(「中国共産党の専制擁護の絶唱」)
われわれにとっても今日の中国経済の性格分析と中国共産党権力の性格規定は急務となっているのだが、ここでは目を転じて「三つの代表」論の大キャンペーンの背後で、それと微妙な関係をもって展開されている一つの興味ある「論争」について見ていこう。それは一九九〇年代に入って開始されたいわゆる「新左派」と「自由主義」の論争である。
この「両世紀にまたがる大論戦」と言われる論争は今後の中国の動向を見ていく上で重要であるように思われる。康暁光もまたこう述べている。
「九〇年代、新左派は理論上重大なことを成し遂げた。・・・実際上、彼らは膨大な理論体系を構成しており、それは一つのイデオロギーへと発展し、さらには中国大陸の権威主義的政治に合法性を提供する論説となる大いなる可能性を持っている。この意義でみれば、九〇年代中国共産党の最大の収穫はイデオロギー再建の分野において初歩的な成功を獲得したことだと言うこともできる」。
つまり「文革徹底否定」と「改革開放」路線の展開のなかで、中国共産党はイデオロギー的には事実上空白となっていたのだが、「新左派」理論の登場はそれを埋めていく可能性があるというわけである。
「自由主義」とは大雑把に言えば文革終焉後に党内「改革派」に呼応した在野の自由派知識人の系譜にあるものとしてわれわれにとっても了解可能な思潮である。だが「新左派」とは何者なのか。
文革崩壊以降、中国において「左派」という言葉は貶義であり、日本では「改革派」との対比で「保守派」と訳されたりしている。ところがその中国に「新左派」が生まれ、その主張を述べ立て、公然と「自由主義」を批判して論争になっているというのだ。
この「新左派」と「自由主義」の論争は多岐にわたっており、その全容をつかむにはかなりの準備が必要である。それに現在主として雑誌やインターネット上で展開されているこの論争が中国の人民諸層の動向とどのように繋がっているのか、さらに中国共産党当局が今のところそれを放任しているかに見えるのはいかなる政治的判断によるのか、等々事態はなかなかつかみ難い。
一九八九年以降、真実を公に語ることは実際には不可能なのであって、誠実な思想は地に籠っており、表に出ているのは多かれ少なかれシニックな日和見的なものであり、この両派の主張をもってこの時期の思想を代表するものとするのは正しくないという見解もある。(任不寐「『日和見主義』の理性的境界」)
それに中国での知識人世界と広大な大衆世界とは今なおわれわれの想像を越えて隔絶したものであるようであり、それに「インターネット論壇」を賑わしているこの論争も伝統的なメディアでは人目を惹いているわけでは決してないという証言もある。だが中国共産党指導部がこの論争を注視しているのは確かである。
ここではそれらは今後の課題として、「自由主義」の代表的な論客である徐友漁、朱学勤の整理を一瞥して先に進もう。彼らによれば対立点は次の諸点をめぐっている。
1.「市場経済と社会的不公平」、2.「グローバル化とWTOへの参加」、3.「中国の国情について」、4.「大躍進、人民公社、文革等々をどう取り扱うか」、5.「八〇年代の思想解放運動と五四新文化運動をどう取り扱うか」、6.「中国の現代化」。(徐友漁「知識界は一体何を争っているのか?」)
見られるようにこれらの論点の背後にあるのは、文革終焉以降の「改革開放」の評価、一九八九年の天安門事件、東欧・ソ連社会主義の崩壊の総括の仕方、そしてグローバリゼーションと「九・一一」のもとでの中国の内外政策という大きな問題である。
朱学勤はそれらはつぎの三つにまとめられると言う。
1.中国の「基本的国情の判断をめぐって」、2.「社会的弊害の判断をめぐって」、3.社会的弊害をいかに解決するかをめぐって」。(「新左派と自由主義の争い」)
以上の諸点はひとり中国にとどまらず、日本のわれわれにとっても大きな関心事である。しかし今までのところこの論争は日本でそういうものとして取り上げられ検討されてきたわけではない。
この論争に注目した日本での数少ない作業の一つに緒形康「現代中国の自由主義」(『中国21』Vol.9 風媒社、所収)がある。興味ある人は参照のこととして、ここでは徐友漁が上げたなかの一つについて見ておこう。それはわれわれにとっても同時代の出来事であった文革の問題である。
なにしろ「新左派」は「われわれは永遠にいわゆる『文化大革命』を呪おう」(胡喬木)ということが国是の中国で「文革にも合理的要素があった」、「傷痕文学的総括から脱しなければならない」と主張しているというのだ。しかもその多くは文革を知らない若い世代だという。
もっとも「新左派」と言ってもその内部は均質ではなく、外国在住派と国内派、毛派と必ずしもそうでない者、ナショナリックな傾向とそうでない者との間にニュアンス上かなりの見解の差があるのだが、「自由主義」批判では一致している。
一方、「自由主義」もまた「市場」万能派と必ずしもそうではなく「社会的公正」と政治改革に力点を置くもの等の差異があるのだが、共に「新左派」の主張には強い警戒心を抱いている。その多くは文革をくぐっており、その一人徐友漁は文革史上名高い四川省成都での大武闘を経験した「出身不好」の元造反派紅衛兵の指導的メンバーの一人である。
この両派が文革をめぐって何を論争しているのか、これはきわめて興味あることである。
1.「新左派」とは何者か――自由派知識人の分岐
ここでは両派の論争全体に立ち入ることはできないが、以下の記述の背景理解のため両派の形成の概略を、とりわけ「新左派」とは何者なのかのおおよその輪郭をつかんでおくことにしよう。
「新左派」は一九九〇年代に新たに登場した「自由主義」に対抗して形成されている。両派の論争が公然化したのは一九九七年だというからごく最近のことである。
「自由主義」とは広義には文革終焉後、政権内部の改革派と連携した自由派知識人、とりわけ九〇年代に大きな影響力を持った新啓蒙主義の系譜上にあると言えるにしても、その系譜には一つの重要な転折点があった。すなわち一九八九年天安門事件と一九九二年鄧小平「南巡講話」の介在である。
天安門事件以後、運動を担った活動家層の中核部分は獄中に入るか「海外流亡」を余儀なくされたのだが、その後の中国思想界を覆ったのは無力感と「失語症」であったという。そしてこの時期それを覆いつくすかのように「改革開放」が全面展開へと向かい、知識人たちの間でも「下海」が流行となる。
しかし次第に「失語症」からの回復が始まり、思想が再形成されていく。そこには二つのベクトルがあった。その一つは「急進主義」の批判であり、もう一つは中国にとっての資本主義の肯定的評価であった。
「急進主義」批判の背後にあったのは言うまでもなく文革総括の記憶と天安門事件の教訓であった。これまでのような体制変革の道は誤りだったというのだ。こうして「新権威主義」、「新保守主義」が主張されることになる。
一方、これまで社会主義中国のもとで一貫して批判の対象だった資本主義とそのイデオロギーの見直し、評価が進行する。こうしてこれまで体制批判で一体感を保持していた自由派知識人の間に分岐が起こり、その一部は体制支持へ移行する。これら思想の再編の中からいわゆる「自由主義」が形成されていく。
この時期、彼らが読込んだのは、バーク『フランス革命論』、トックヴィル『アメリカにおけるデモクラシー』、ハイエク『隷従への道』、バーリン『自由論』、アレント『革命について』、ポパー『開かれた社会とその敵』、等々であった。一つのエポックを画する運動の挫折の後の光景はいずこも同じなわけである。七〇年代、われわれもまたこれらの著作を手にしたではないか。さらに中国近代史のなかから「急進主義」、「民衆主義」(「民粋主義」)とは異なる自由主義の系譜が発掘され、顧准、陳寅恪等の再評価がなされている。
「新左派」はこの「自由主義」の主張――「急進主義」、「民衆主義」への拒絶と中国にとっての資本主義の積極的意義の評価、市場化の先に政治的自由と民主を展望する――への批判者として登場している。本格的な論争の始まりは一九九八年に発表された韓毓海の「『自由主義』というジェスチャーの背後で」という文章であった。
ここではこの「新左派」について二点を留意しておこう。その一つは「新左派」もまた広義の自由派知識人の流れにあり、彼らによる「自由主義」批判が結果として中国共産党政権による自由派への批判、圧迫と交錯することがあるとしても、それを一緒くたにはできず、この論争は自由派の分岐としての性格を持っていることである。
もう一つは「新左派」の内部には明らかに異なる二つの傾向があり、人的に見れば一方の汪暉、崔之元らのどちらかと言えば学者派と、他方での李憲源、粛喜東ら「民衆派」との間の見解、出身階層、社会的基礎のちがいである。「自由主義」の王思叡は李憲源らを「新左派」、そして党内の「老左派」とも区別して「中左派、毛主義」と名づけている。(「今日の中国の左派のスペクトル」)
後でふれる演劇「チェ・ゲバラ」の製作者張広天、黄紀蘇らは典型的な「中左派、毛主義」であり、彼らは「新左派」の学者部分が「革命」について語ることのないのを皮肉っている。(張広天「『新左派』と革命の問題から私の文芸観を語る」)
2.両派の文革論争を見ていく視角
ところで文革をめぐる両派の論争についてある評価を下すためには文革についての今日的な総括的評価を必要とするわけだがこれがなかなか難しい。ここではつぎの諸点を押さえておくに留めよう。もっとも視角が定まりさえすれば文革評価の基点は半ば築かれたことにはなる。
まず第一点は文革終焉以降今日に至る中国共産党の「文革徹底否定」論は退けられなければならないということである。 多くの悲惨さを伴った文革を今日単純に肯定するものはいない。のちに見るように「新左派」にしてもそれは同じである。だが「文革徹底否定」論が文革の真剣な批判的総括であったかといえばそうではなく、それは勝者たちの政治的見解であった。
「『四人組』の反革命クーデターを粉砕したもの」とされた一九七六年一〇月六日の「四人組」打倒は形態的に見れば実は反文革派の「クーデター」であった。葉剣英ら軍人を中心に秘密裏に準備された「特殊な戦闘計画」に対して政治闘争による権力掌握を意図していた江青グループはひとたまりも無かったのである。
その後、文革の悲惨な実態が衝撃的に明らかにされ、すべては「四人組」と追随者たちの「内乱」の企てだったとされて以降、世界の文革評価は逆転し、日本の「文革礼賛者」たちも沈黙してその総括を放棄した。
だが、その「文革徹底否定」論は、①文革前の十七年は正しかったのであり、「走資派」など存在しなかった、②造反派とは「三種類の者たち」すなわち「林彪、江青グループに追随して造反し出世した者、派閥意識の甚だしい者、殴打・破壊・略奪分子」のことである、③社会主義とは生産力の発達である、という把握に基づくものであり、そこからは文革に立ち上がった億万の造反派大衆の存在と彼らが感受していた中国社会主義の抑圧性の問題はスッポリ抜け落ちていた。
文革は毛沢東なりにこの「官僚主義」の問題に取り組もうとしたものであり、その打破を「公然かつ全面的に広大な大衆を下から上へと立ち上がらせ、われわれの暗黒面を暴き出す形式、方式」をもっておこなおうとしたものであった。
だが劉少奇らの異論を「党内ブルジョアジー」と規定したことに示されるスターリン主義的な他者批判の仕方の全面化、それら「走資派」への「革命的大批判」の激烈な展開にもかかわらずそれは「免官革命」、「人を捉まえる革命」――のちに造反派の鋭敏な部分が揶揄してそう名づけ批判したのだが――でしかなく、根本的な社会的・政治的変革への道は閉ざされていたこと、その理論的根拠となった毛沢東、張春橋の「ブルジョア的権利の制限」論の理論的・実践的誤り、等々によって、文革は仮にそれが勝利したとしてもその「共産主義」の中身は「コミューン」ならぬマルクスの言う「粗野な共産主義」を越え出るものにはなりえなかったろう。
劉少奇、鄧小平の路線に文革前の中国社会主義の抑圧性が含まれていたのは事実だとしても、それでは毛沢東の文革と鄧小平の「改革開放」のどちらが中国の民衆にとって望むべきものだったかと問題を立てたとき、「改革開放」をただブルジョア階級の復活への道だと割り切れないところに文革総括の難しさがある。それはちょうどソ連・東欧の社会主義の崩壊をどう見るのか通ずる問題でもある。
かって毛沢東の文革を越えた「中国コミューン」を唱えた造反派の指導者たちも今日それを唱えることはしていない。
しかしこれらの問題に納得いく総括を深めるためにこそ「文革徹底否定」論は突き崩されなければならないのである。
第二点は文革が確かにはらんだ「誤り」、否定的な問題性をどう押さえるべきなのかという問題である。それは毛沢東の文革理論の誤りとそれを利用した「四人組」の「反革命的内乱」の結果だったというのが「文革徹底否定」論の主張である。
この主張を退けたとしても、そこには「文革徹底否定」論が言う意味とは異なる意味での「毛沢東の文革理論の誤り」があり、中央文革と造反派、林彪勢力、「四人組」によるその実践があった。そしてそれは反文革派の凄まじい抵抗に遭遇する中で多くの悲惨な出来事が起こった。そして文革を文革たらしめた造反派の運動が毛沢東の指導の枠をはみ出たとき「今は紅衛兵少将たちが誤りを犯すときである」(毛沢東の不可思議な言葉)として解体され、以後文革は枯渇へと向かっている。
しかしそれらの諸事態を一つ一つ吟味していくとき後知恵的に見えてくる毛沢東理論の個々の誤りという次元を越えて浮かび上がってくる一つの事柄がある。それは文革が課題としたことの困難さ、さらには「革命」そのものの困難さが突きつける問題である。どういうことか。
現実がある課題をのっぴきならぬものとして突きつけ、人は手持ちの認識と実践力をもってそれに取り組み解決しようとする。その「解決」の仕方そのものが一歩間違えれば単なる「誤り」を越えて「悪」を構成してしまうことが起こる。 毛沢東と文革派は彼らがのっぴきならぬものと考えた課題と取り組み解決しようとした。
「誤り」はこの困難な課題との格闘の中から生じている。これが基本である。つまり「誤った路線」だったから誤った結果が出たのではなく、ある現実が突きつける課題との格闘がまずあり、もし「誤り」が生じるとすればそれはその格闘の仕方、解決の仕方の中からなのだととらえるべきなのである。
理論的に未熟な者が「誤り」を犯した、当初からの悪人が「悪」をなしたというようなことは政治の世界では問題になりえないのである。そもそも「誤った路線」そのものが何かとの格闘の敗北形態、堕落形態なのである。
このように言うことは文革の救出のためではない。そうではなく問題をこう立てることによってはじめて文革の「革命的批判」が可能となるのである。
第三にこうして文革はそれが単なる「野心家たちの反革命的内乱」などでなかったからこそ問題は深刻なものとなった。それは億万の大衆を立ち上がらせる力を持ったのだが、直面した課題との格闘、その解決の仕方そのものが「誤り」を生み出し、「悪」を構成し、そこでは政治と政治言語の邪悪さはその極限的な姿を現している。
しかし注目すべきはそれら文革の邪悪さ、抑圧性の只中から、それを対象化しつつ毛沢東の理論、政治、言語から自立していく動きが始まっていることである。「新思潮」、「極左派」の形成である。湖南省無聯の「中国はどこへ行く?」や「李一哲大字報」はその流れの中から生み出されている。
だがそれらの動きは一つの運動としての文革の敗北を意味していた。こうして文革派から人心が離反した分だけ、それは反文革派に集まり文革は打倒されたのである。
今われわれがあらためて文革について考えるということは他でもなく、東欧・ソ連の崩壊を「スターリン主義の崩壊であり、真のマルクス主義は無傷である」とする欺瞞に留まることなく、かつ勝ち誇る資本主義世界からの「マルクス主義は崩壊した」という大合唱に抗して歴史と現実を再点検し、針路を再設定するという困難な課題の一環としてである。 そしてこの問題の総括はいまなおなされていないのであり、それはソ連・東欧社会主義のみならず日本のわれわれ自身の運動の衰退・凋落の総括に直接に関わる問題でもある。
それではこの文革評価をめぐって「新左派」、「自由主義」は何を争っているのか。
3.「新左派」の文革再評価
文革の意義を見直すべきだという大胆な発言を最初におこなったのは崔之元だといわれている。一九六三年生まれで中国社会科学院に入った崔之元はその後アメリカに留学し、シカゴ大学、マサチューセッツ工科大学で教鞭をとっている。 その論文「鞍鋼憲法とポスト・フォード主義」で鞍鋼憲法こそポスト・フォード主義の先駆だったと述べて論議を呼んだ崔之元はさらに文革についてこう述べたのである。
「『文革』大衆運動の中にもある合理的要素を含んでいたことを見るべきである」。
「それは大衆の政治生活への参加である」。
「ニーチェは、記憶は一民族を殺すことができると述べたが」、文革の傷痕を反芻するだけ では駄目である。
「盥の水と一緒に赤ん坊を流してしまってはならない」。 「毛沢東が述べた七、八年たったらもう一度文革をやるという言葉は定期的な全国的直接普通選挙ととらえるべきであり、これこそが人民民主独裁あるいはプロレタリア独裁の本質なのである」。
文革から三〇年余をへた今日、こういう主張が登場したのである。当然これらは中国国内で強い反発を受けると共に共鳴も生み出している。まず「新左派」の中で文革について積極的に発言している崔之元、李憲源(常仁)、粛喜東らの主張について見ておこう。
その内部は必ずしも一様ではない「新左派」だが、ことを文革に絞ったときそこにはさらに明確な見方の差がある。ここで取り上げる論者で言えば、崔之元のそれが西欧の現代理論によってとらえ返された文革再評価だとすれば、青年期に文革後期の「批林批孔」運動などを体験している李憲源は心情的にも毛派であり、民衆の立場の名において「経済文革」の必要性を唱える実践派である。彼は「新左派」と呼ばれることを必ずしも歓迎しない崔之元らを皮肉ってこう述べている。
「私は西欧理論の大作を学ぶことにものぐさであるという欠点を持っており、それにかって地球の裏表の地で肉体労働者として働いてきたので、西欧の深遠な左翼理論を売り出すことに長けているという『新左派』としてもふさわしくない者である」。
もっとも、李憲源のこの批判を「『新左派』の分岐を示すもの」と見る「自由主義」の論評に対して「左派、民族主義陣営内部の意見の分岐を無限に誇張している」と反論しているところを見ると、これらはイデオロギー的にいまだ生成過程にある「新左派」の内部論議なのかも知れない。
1.「文革徹底否定」の批判
彼らはその主張に当たって共にこれまでの当局による「文革徹底否定」論の弊害について述べている。
崔之元:「王紹光が『文革研究の視野を広く開拓しよう』でまさしく指摘したように、当局が今日おこなっている文革研究への制限は『安定団結』を追及するという妥当な願望によるにしても、実際にはわが民族が文革の深刻な教訓を全面的に汲み取る上で不利なものとなっている。文革の複雑な社会的原因についての公開的な自由な学問的検討をおこなうことによってはじめてわが国が『安定団結』の民主的な法制への道を歩む上で真に有利となるのである」。(「毛沢東の文革理論の得失と『モダニティー』の再建」)
李憲源:「あらゆる『一〇年の動乱』、『一〇年の悪夢』の類の言い方は感情的な共感を広汎に引き起こすことが容易だとしても、文革中の異なる人々の『受難』の異なる性格、異なる社会的根源を分析することに役に立たない。文革に対する社会科学的な研究は『傷痕文学』的な視野を越え出ることがどうしても必要なのである」。(「造反派と五七年の右派との共通点から見た文革」)
そして李憲源は「文革徹底否定」論がもたらした諸結果をつぎのように列挙している。
1.「人民大衆の民主的監督の権利と参政意識を弱め、官僚の特権と腐敗の風潮を助長した」。2.「『大民主』の有益な試みとその改善を放棄し、社会矛盾を激化させ、国際的な敵対勢力が機に乗ずるのを許した」。3.「『法制を軌道に乗せる』を一面的に強調することにより、司法の腐敗を中国の法治の建設にとって巨大な障害となさしめた」。4.「労働人民の政治的、経済的地位を弱め、貧富の両極分化を改革と社会進歩の代償とした」。
李憲源はそれらの内容を詳細に述べているのだが割愛しよう。
粛喜東:「遺憾なことに今日流行の文革歴史記録の文献の中で、その大多数は『劫後余世(大災難を幸せにも生き延びた)者の回想録文学』という類型のものであり、この類の文献は文学化、エピソード化ということの他にはそれらの大半は事後の回想者、夢から醒めた者、懺悔者としての視角、言語、価値観から書かれたものであり、文革参加者が当時関心を持ったテーマを反映したもの、参加者の当時の思想性格と言語のスタイルを反映したものは今日ではきわめて見つけがたく、関連文献の系統的整理が欠けていた」。(「文化大革命文献館 前書き」)
「文化大革命文献館」というのは粛喜東が主宰する貴重な文革資料を集めたサイトであり、彼は香港の社会学者だということだが細かい経歴は分らない。
それにしてもこれらは何とも大胆な発言である。文革総括の見直しは「安定団結」にとって必要なことなのだと強調しているとしても、従来の「文革徹底否定」論的反省は公然と批判されている。現在の中国でこの程度のことを言うことは許されているのか、それとも「新左派」がその内部に多分に中国ナショナリズムに繋がる要素を含んでいることもあって当局が容認しているのか。
もっともここが微妙なところなのだが、「新左派」の文革再評価は当局の「文革徹底否定」を直接批判の対象とすることなく、専ら「自由主義」の文革総括への批判としてなされている。ここにはただ戦術というにとどまらない「新左派」の思想性格が現れている感もある。
ところで当局の文革総括に異を唱える声が「新左派」以前になかったわけではない。かの湖南省無聯の楊曦光、「李一哲大字報」の王希哲、広州「旗」派の劉国凱、紅衛兵組織発足の地、精華大学付属中学出身で作家の鄭義ら、かっての造反派紅衛兵の指導者たちの一部が自らの経験に照らして官方文革史の記述を批判してきている。
そこでの文革経過への歪曲、とりわけ文革のすべての「悪」を造反派紅衛兵の仕業とし、その活動を全否定した当局の総括の仕方は容認できることではなく、彼らは文革には「毛沢東の文革」と「人民の文革」とがあったのであり、その関係は「相互利用」だったという「二つの文革」論、そしてこの「人民の文革」は一九六六年六月から六八年秋(あるいは六九年春)の間だったという「文革二年(あるいは三年)」説をもって対抗し、自分らの活動こそ今日の「民主化運動の先駆だった」としてその意義を再確認してきている。
「新左派」による文革再評価も彼らの作業に助けられている。だが「新左派」の文革再評価には元造反派イデオローグたちのそれとは大きな違いがあった。それは彼らが毛沢東と中央文革の文革そのものに「合理的な要素があった」としていることである。そしてそれと造反派との関係は「政治的同盟」だったと言う。
なお、この「相互利用」だったのか、あるいは「政治的同盟」だったのかは文革を見ていく上で重要な論点だと思われるが「新左派」はそれをめぐって元造反派イデオローグたちと意見を異にしている。
さらに「新左派」の主張には造反派たちのそれとは明らかに異なるトーンがあった。それはインターナショナルな立場に立っての革命の復権というのではなく中国ナショナリズムに繋がる文脈のなかでの文革再評価であるということである。
2.「文革の積極的要素」
「新左派」たちによる文革再評価の特徴は、それが単なる「文革ノスタルジー」(「文革情結」)によるのではなく今日の世界と中国の新たな情勢に突き動かされていることにあった。
その一つはその主張が欧米諸国での新たな資本主義批判の理論的摂取に媒介されていることである。フォード・システムの克服を唱えるレギュラシオン理論から、アミン、サイード、ウォーラーステイン、「ポスト・モダン」理論などを学んだ彼らの目に毛沢東理論の幾つかはすでにそれを先取りしていたものとして映り、こうして文革の意義が再発見されたわけである。
もう一つは「改革開放」がもたらした状況への危機感である。「改革開放」は一方で大きな社会的境遇の差を生み出しており、流れから取り残された層のなかに一方で「毛沢東ノスタルジー」(「毛沢東情結」)が生まれ、他方「法輪功」の社会的基盤となっている現実があった。
その深刻さは批判派の何清漣とは言わず今日の体制下で一定の位置を占めている一部の「新左派」たちによっても「目下、中国は再び社会的不安定の時期に入りつつある」との警告が発せられているほどのものとなっている。(王紹光、胡鞍鋼「最も厳重な警告:経済的繁栄の背後での社会的不安定」)
「新左派」の張広天、黄紀蘇らによる演劇「チェ・ゲバラ」が二〇〇〇年四月の北京公演を皮切りに、河南、上海、成都、香港、広州等の中国各地を巡回して多くの観衆を動員して強い感銘を呼び起こし、著名人による劇評が幾つも書かれたというのも時代の雰囲気を示していた。
そして「改革開放」によって中国が乗り出した世界はアメリカが圧倒的な支配力を握っており、そこの秩序に飲み込まれるのではないかという危機感もあった。旧ユーゴ中国大使館「誤爆」事件は中国ナショナリズムを一気に高めている。
(1)「毛沢東理論はポスト・モダンの先駆だった」
「新左派」にとって毛沢東理論は「反資本主義的モダニティーのモダニティー理論」(汪暉)として押さえられている。彼らによってとらえ返された文革理論はつぎのようなものであった。
崔之元:「『文化大革命』は悲劇をもって終わった。だがこのことは毛沢東の『文革』理論が正統マルクス・レーニン主義の重大な乗り越えを意味していなかったことを意味せず、さらには『大民主』――広大な労働人民の経済民主と政治民主――は望むべくして及び得ないものであったことを意味しない」。
「われわれは西欧主流のモダニティーの中での正統マルクス・レーニン主義の位置について深刻な認識をしっかり持たなければならない。毛沢東と正統マルクス・レーニン主義との関係はすなわち中国での実践と西欧主流のモダニティーとの関係なのである。この関係の深刻な認識があってはじめてわれわれは新たな『言語』を創出できるのであり、中国の現在と未来を描き把握できるのである」。
李憲源:「指摘しなければならないのは、文革後期、毛沢東は大局の安定、官僚階層との妥協の必要性によって造反派への大規模な打撃・迫害を黙認さらには放任したとはいえ、文革運動は結局のところスターリン主義的な社会主義の方式の伝統と決まりを創造的に突破したということである」。
そして崔之元は毛沢東は「正統マルクス・レーニン主義」も超えることができなかった「西欧主流のモダニティー」が抱えていた「深刻な内在的矛盾」を突破したのだと言う。
「解放」と「規律」がそれである。
「毛沢東の新たな思想の核心は『人民大衆が歴史を創造する』ということであった」。
「毛沢東は『人民大衆が歴史を創造する』という理論をもってヨーロッパの主流であるモダニティーがはらむ矛盾の突破を試みた。彼が文革の中で唱導した『大民主』こそ『人民大衆が歴史を創造する』ということの大実践であった。この実践は悲劇をもって終わりを告げた(その部分的な原因は毛沢東の文革理論それ自身が正統マルクス・レーニン主義の教条性を超越するのに不徹底だったことにあった)とはいえ、その経験の教訓はわれわれが二一世紀の中国の政治、経済体制を建立するための豊富な参考を提起している」。
こでは二つの点にふれておこう。 第一にマルクス主義がこの「内在的矛盾」を超えられなかったという点について。
崔之元の場合「正統マルクス・レーニン主義」、「教条化したマルクス主義」という表現が区別されないまま用いられているのだが、本来のマルクス主義においては彼の言う「内在的矛盾」は自覚されており、従ってそれを超える端緒はつかまれていた。
「この共産主義は人間と自然とのあいだの、また人間と人間とのあいだの抗争の真実の解決であり、現実的存在と本質との、自由と必然との、対象化と自己確認との、自由と必然との、個と類とのあいだの争いの真の解決である」。(『経済学・哲学草稿』)
マルクスはその鍵を「プロレタリアートの社会的結合」としてとらえていた。(この問題については別の角度から斉藤論文(「解放派におけるマルクス主義の深化再生の道は何か」、本誌創刊号に抄録)が詳述している。関心ある人はそちらを参照していただこう)
もっともマルクス主義がこの「矛盾」を解決したと言ってもそれはあくまで端緒としてであり、その実現は困難な実践的・歴史的課題であった。
「プロレタリアートの社会的結合」は資本主義そのものが生み出すのだが、それはあくまで萌芽であり、その実現をめぐってすべての困難さが現れる。なぜ困難なのか。それは「内在的矛盾」の解決、「プロレタリアートの社会的結合」の実現は予定調和的なものではなく実践を通して形成される課題であり、その過程はこれで終わりということではない永続的なものだからである。
つまりそこには「相対的な正しさ」や「妥当な真理性」はあっても「これが客観的真理」と誰かが言明しるものはないのであり、こうして課題はその実現のための過程、条件、過渡的課題の解明という領域に転移する。「情勢分析」や「戦略・戦術」が課題となる。政治と政治言語がその真価を問われるのはこの領域においてである。
そして政治的異論、政治的他者が立ち現れるのはこの領域においてである。「客観的真理」が不在ないし未実現のもとで、複数の選択肢がいわば「相対的な同等性」を持って登場するのは避けられない。こうして争われるべきは相互の消し合い、政治言語の死滅を意味する「絶対的、客観的」真理ではなく、「相対的、妥当な」正しさ、真理性なのであり、だからこそ対立と共同、論争は政治と政治言語の本来的な属性なのである。
第二に崔之元の主張に反して毛沢東理論はそれを超えていないという点について。
なぜなら毛沢東理論に欠けていたのはまさにこの「プロレタリアートの社会的結合」論だったからである。
「大民主」を意味するとされる「人民大衆が歴史を創造する」という言葉が実際に人民大衆の自立を含んでいたのなら崔之元が「問題は解決された」と言うことはできよう。そしてこの人民大衆の自立には複数の選択肢を前にして自らの見解を持ちうること、言い換えれば毛沢東をはじめとする党中央の意見に対しても異論を持ちうることを意味する。
だが「大民主」はそういう意味での自立を容認するものではなかった。そこでは指導的な意見以外は容認されないというより、人々はそれに自己解体的に一体化することを求められたのである。
さらに中国共産党のマルクス主義、毛沢東理論が伝統的に持つ政治的他者観がある。これについては後に見よう。
以上の問題に無自覚のまま崔之元はつぎのように述べている。
「今日の『ポスト・フォード主義』の世界的潮流の中で毛沢東が高く評価した『鞍鋼憲法』は最も早くかつ鮮明にフォード式分業体制の骨化に挑戦したものとして、とりわけ人々の注目を引いたのである」。
ここで崔之元が「経済民主」へ引き継ぐべきものとして注目しているのは「両参一改三結合」であった。
「一九五〇年代末の大躍進期に提唱された企業の大衆的管理と技術革新活動の方式。『両参』とは労働者が管理活動、たとえば生産労働のほか、コスト、技術措置などの計画編成、製品の品質分析、設備の検査維持、新製品の研究開発、技術規定の編成などに参加する一方、指導幹部が毎年一定の時間、労働者と一緒に現場労働に参加し、現場労働者の要求と生産上の問題を適時に解決することを指す。『一改』とは生産技術の発展に適応しない規則制度を『両参』に適合したものに改革することを指す。『三結合』とは指導幹部、技術者、労働者の三者の協力による技術革新運動を指す。この方式はのちに鞍鋼憲法に継承され、文化大革命期に強調された」。(『岩波現代中国事典』、1999)
崔之元は「それはフォード式の骨化した、垂直的命令を核心とする企業内分業理論への挑戦であった。『両参一改三結合』は今日流行の用語でいえばチームワークのことである」と言う。
「遺憾なことに、『鞍鋼憲法』の発祥の地で、今日人々がそれを再び提起することはほとんどない。その原因は複雑だが、一つはっきりしている原因は、『大躍進』と『文化大革命』の中で出現した混乱が『鞍鋼憲法』の執行においてその元々の意図との違いを極端に大きなものにしてしまったことであった。現在の問題は、われわれが盥の水と一緒に赤子を流してしまうべきか否かということである。『改革開放』の今日にあって、世界的な『ポスト・フォード主義』の潮流のなかで、『鞍鋼憲法』はわが民族の工業振興にとって精神的、組織的資源の一つとすることができるのかできないのか?」
「新左派」たちによる過去の経験のこういう再評価の仕方には心惹かれるものがないわけではない。文革そのものがはらんだ深刻な問題性と、とりわけ「文革徹底否定」論によって今日では塵あくたとされている実践のなかからその初源の意図と経験を救出し、それを今日の実践に繋げるということは意義あることであり、人を元気づけるものだからである。
だが「新左派」たちの文革総括の仕方、毛沢東の文革理論の評価の仕方には、その多くが文革をわが身で経験していないことをさておいても、やはり理論的未熟さ、皮相さがあると言わなければならない。
ここでの問題でいえばそれは毛沢東の「鞍鋼憲法」論そのものがはらんでいた問題に無自覚なことである。それは文革の混乱によってその「元々の意図」が捻じ曲げられたというものではなかった。その「元々の意図」そのものに「新左派」がイメージする「経済民主」は含まれていなかったのである。
そしてこれこそが文革をその根底において失敗づけた重要な一因だったのであり、毛沢東の本来の文革目的であった「闘・批・改」を通しての「新生事物」の実現、「真紅の新世界の創出」は文革後期、江青グループの主導のもとで戯画的なものとなり、鄧小平による絨毯爆撃的な「整頓」によって掘り崩される脆さを持っていた。
そのことに気づいた毛沢東がおこなったのは以前からの持論であった「ブルジョア的権利の制限」の前面化であり、張春橋、姚文元にその文章化を命じている。
だがそれは「ブルジョア的権利」を死滅させていく社会的諸関係の形成へ向けての方策の具体的提起ではなく、現今の生産関係のなかから「走資派」を放逐すれば「ブルジョア的権利の制限」が可能となるといった理論的にも誤った把握に基づくものであり、長年の「大批判」に倦んだ労働者大衆を奮起させることはすでにできなかった。
だがこの問題は文革の限界をこのように見るわれわれ自身が実践的にはもとより理論的にも未完の課題なのであり、人のことを言えた義理ではない。「アソシエーション革命」論もいまだその遙か手前にとどまっているというのが実情なのだから。
(2)「大民主」の意義
一九六六年八月、「十六条」(「中国共産党のプロレタリア文化大革命に関する決定」)が呼びかけた「大民主」(「大鳴・大放・大弁論・大字報」)は当時の造反派の運動を一気に解き放ったものであった。
「新左派」たちの文革再評価はニュアンスの差を含んでいるが、彼らが一様に強調しているのは「大民主」の意義である。
崔之元:「毛沢東の『大民主』は毛沢東の未完の事業であり、彼の政治的遺産の中でわれわれが最も重視するに値する部分である。毛沢東の文革理論を弁証法的に止揚することは二一世紀中国の高度な民主的政治体制を建設するための必要条件なのである」。
李憲源:「社会主義的民主の進め方という角度から見れば、そのなかで最も重要な一つは文革が大衆に『四大』の形式をもって『プロレタリア階級の司令部』を除いて上は中央副主席から下は生産現場の支部書記に至るすべての党組織の指導部を暴露し批判することを許したことにあった。・・・もし広大な民衆の中に辛亥革命も一九四九年の建国も完成できなかったこのような思想革命が完成していなかったなら、のちの思想解放も改革開放も考えられなかったろう。だからこの種の文革の積極的要素を改革開放と対立するものと見なすことはまったく道理がないことなのである」。
粛喜東:「文革の意義をさらに全面的に総括する上で、われわれは『人民内部の矛盾を正確に処理する』という方式を元に文革を人民内部の矛盾を処理する方式を探求する大胆な試みと理解することである」。 「『十六条』の中の第七条は、革命的大衆を『反革命』と見なす者を警戒せよと述べているが、これは時代を画する意義を持つ社会主義の『権利法案』に相当するものである。文革のこういう意義での試みは痛ましくも失敗した。だがつぎのことは否認されるべきではない。すなわち文革運動は一時期に亘って、膨大な数の参加者がパリ・コミューンと言う理想の旗印を掲げて社会主義が本来含んでいた中心的内容――人民大衆が国家の上層建築を管理すると言う権利、今日の言葉で言えば政治生活における民主――をまさに実践したのである」。
このようにこれら「文革の積極的要素」の見直しは単に文革の再評価ということにとどまらず、今日の「改革開放」の推進に利するものであり、さらにはヨーロッパ民主主義を超えた「高度な民主主義」建設の中に生かされるべきものと位置づけられている。
そしてこの主張の背後にはソ連・東欧の崩壊に対する次のような総括があった。
韓毓海:「社会主義のスターリン主義版は生産手段の所有制の真の改造をおこなったわけではなく、市場の廃止後の空白は国家官僚によって補填されたのであり、国家官僚が実際に演じたのは資本家の役割であった。人民にはただ名義上の政治と経済への参加の権利があったのであり、実際にはこの権力の操縦は少数の官僚の手に握られていた。
この合法性の危機の解決には二種類の方案があった。その一種は民主的参加の方式と道筋を拡大することによって政治領域をますます公共的なものとすることである。もう一つは実際上はコントロールされた上から下への市場化と私有化であり、少数の者に生産手段を掌握させ、匿名のものを公開のもの、合法的なものとすることであった」。(「『自由主義』のジェスチャーの背後で」)
そして「自由主義」への批判は彼らが後者の道を歩もうとしているということにあるのだが、その正否はさておき「新左派」のこれらの「大民主」の評価にはいかにも甘さがあった。 中国共産党言語(毛沢東言語)には人を戦慄させる威嚇の言葉と共に魅惑的な解放的言語が数多くある。「思想改造」(「翻身」)、「生き生きした政治的局面」、「人民内部の矛盾」等々である。文革初期の「群衆自己解放自己」、「群衆自己教育自己」などはその最たるものだろう。
だがそれらが政治的に開かれた空間、自由な空間とは、まったく異質なものへと展開する契機を含んでいたことを「新左派」は理解していない。
たとえば「思想改造」は人を旧来の諸関係、価値観からの解放であると共に「思想改造」の組織主体への思想的、政治的従属を意味した。また「人民内部の矛盾の処理」はそこで相対立する矛盾相互の相対的同等性の原理的承認を意味せず、常に「正しいもの」、「進んだもの」への「間違ったもの」、「遅れたもの」の包摂、吸収を意味した。
「生き生きした政治的局面」も同じである。この言葉は造反派紅衛兵たちに開かれた政治空間のことと理解されて彼らを魅了した。だがそれは複数の選択肢のもとでの異なる意見間の対立と共同の政治空間を意味せず、あくまで「正しい思想」に統一され、一体化されることを前提とした上での、「積極分子」たちの活発な活動世界なのである。
「新左派」たちは総じて毛沢東の「解放性」がはらむこの側面には気づいているのかいないのか無批判的なままである。
3.文革をどう総括してはならないか
だが「新左派」たちも文革がはらんだ深刻な問題に無自覚なわけではなかった。だが文革はどう総括されてはならないかという点に彼らの関心はおかれている。
汪暉:「現代の中国の革命についての反思における基本的な傾向は革命の〔良くない〕結果(新たな不平等と社会的専制)への批判が革命の歴史的条件の分析に取って替わってしまっていることである。ここで根本的なことは、革命の歴史の中での悲劇をどう弁護するかということでは決してなく、この悲劇をどう理解するか、この悲劇と植民地主義、資本主義の市場拡張と中国社会の歴史的条件との関連をどう理解するかということである。・・・だから真の問題は平等という価値とそのための社会的実践を簡単に否定することではなく、なぜ平等を目標とした社会運動自身がその内部に新たな等級性を生み出したのか、その歴史的メカニズムは何なのかということである」。(「一九八九社会運動と『新自由主義』の歴史的根源」)
海外派の崔之元と共に「新左派」の理論的イデオローグである大陸在住の汪暉は崔之元や李憲源のようには文革の意義について語ることは少ないのだが、以上のように文革の問題性を「悲劇」と見ることのなかにその文革観は示されている。 そして彼らは「文革徹底否定」論を突き崩し、文革の真の姿を復元した後はじめて文革がはらんだ問題の総括も有益なものとなると言う。
李憲源:「新たに生まれたいかなる民主制度もある種の欠陥を避けられないように『四大』もまたその実際の運用の中で必然的に幾つかの問題を生み出した。しかし非常に成熟した西欧の普通選挙制度もまたヒトラーに権力を握る条件を与えたことを考えるとき、『四大』が野心家や陰謀家に操縦されて利用されたことをもってこの制度を廃棄する理由とするのは妥当ではない。この豊かな中国社会主義の特色ある民主制度を改善し完全なものとしていく立場から出発するのではなく、『盥から赤子を流す』軽率なやり方は権力を私有化し、権力で私腹を肥やすことがますます頻繁となり止め難くなるにつれて、そのマイナスの影響はますます はっきりし不断に暴露され明らかになるだろう」。
粛喜東:「このような意義から文革を評価するとき、自ずから文革の是非功罪、とりわけその誤謬を然るべく分析することが可能となる。たとえば階級闘争理論の混入によって作り出された誤り〔原文「失誤」〕、文革初期での陰謀論の横行が作り出した悪い結果、大衆が大民主を実践する上での失敗、等々である。当然これら一切の分析は、転倒され、ごちゃごちゃにされ、隠蔽された歴史を明らかにした後ではじめて議事日程に上がるものである」。(「一九六六年の五〇日:記憶と忘却された政治」)
これらの総括の仕方は首肯できるものである。当初の「良き意図」がいかなる脈絡のなかで「悪」を生み出したかということの解明こそが意味を持つからである。それでは「新左派」たちは何を解明しえたか。
(1)毛沢東と文革の二面性
「新左派」たちも「文革の失敗」について語っている。
李憲源:「毛沢東は文化大革命の実践の過程で、急進的かつ強烈な平民主義的色彩を持った『毛沢東主義』と権力の集中と官僚的秩序を強調する『スターリン主義』との間で常に態度を決めかね、揺れ動いていた。私が思うには、この政治的決断と価値判断における動揺、ジレンマが文革を失敗に導いた重要な原因の一つとなったのみならず、中国の資本主義勢力に再び巻き返しを許したことで毛沢東が歴史的責任を負うべきことだったかも知れないのである」。(「協同を選ぶのか、対抗に向かうのか」)
粛喜東:「言語表現においてまた実践上でも、伝統的な『階級闘争』と大衆の大民主とが衝突する矛盾が存在した。この期間、『革命は客を招いてごちそうすることではない、・・・』という言葉と『武闘はただ皮膚に触れることができるだけだが、文闘によってはじめてたましいに触れることができる』という言葉が両方ともしばしば引用された。前者は伝統的な意味での階級闘争を指していた。後者は特殊な意味での階級闘争、すなわち思想闘争を指していた。そして思想闘争は本来なら人民内部の矛盾の解決形態、すなわち民主的弁論を用いるべきものであった。しかし文革の全過程を通じて両種類の言語、両種類の区別はいまだ明確にされてはいず、それらの間の矛盾、衝突もまた解決に至っていなかったことが、大民主の実践の失敗の伏線となったのである」。(「文革の中の指導者と大衆:言語、衝突と集団行動」)
文革はその発端から、「綱領」次元においても「二面性」を抱え込んでいた。すなわち「走資派」体制の「全面打倒」か「部分改善」かの問題である。「上海一月革命」の当初は「階級と階級の闘い」と述べていた毛沢東は「上海コミューン」への動きに直面して張春橋に「部分改善」だと明言し、以後一部の造反派の「すべてを打倒する」は誤りだとされていく。
「新左派」はこの「二面性」を「平民主義的な毛沢東主義」と「官僚主義的なスターリン主義」、「大民主言語」と「階級闘争言語」との関係と理解している。だが実際にはこの「二面性」は先に「大民主」の個所でふれたように「平民主義的な毛沢東主義」、「大民主言語」それ自体がはらんでいるものと押えるべきなのである。
つまり「新左派」にとって文革の失敗とは、毛沢東の文革理論がはらんでいた新しい要素が同時に並在した古い要素に妨げられて十分その力を発揮できなかったということなのだが、問題の所在はそこにではなく、まさにその新しい側面そのものに「大民主」は構造的に含まれていなかったのである。
(2)「走資派」規定の問題
劉少奇らを「ブルジョア階級の立場に立つ者」と規定したこの「走資派」論こそ「文革徹底否定」論が誤りだと厳しく批判したものだが、「新左派」もそこに問題があったことを認めている。
崔之元:「毛沢東文革理論の積極面は毛沢東が正統マルクス・レーニン主義を突破し、『大民主』と結びついていない生産手段の共有は人民が主人となった社会主義の方向を決して保障するものではないと断定したことにあった。しかし毛沢東の文革理論には重大な誤り〔原文「失誤」〕があった。その核心はやはり彼がマルクス・レーニン主義の教条主義的な制約を脱することができていないことにあり、『大民主』制度の建設に適合した新たな『言語構造』を創造できなかったことにあった。彼の『党内走資派』、『共産党内のブルジョア階級』という言い方はマルクス・レーニン主義の教条的な『旧言語構造』から十分に脱することができていないことに由来しており、それは実際の運動のなかで常に誤って用いられ、毛沢東の最初の意思と異なる結果を生み出したのである」。
粛喜東:「文革の意義をさらに全面的に総括するに当たって、われわれは『人民内部の矛盾を正確に処理する』という範例に立ち戻り、文革を人民内部の矛盾を処理する方式を見つけ出す大胆な試みと理解しよう。・・・文革を人民内部の大民主をおこなう大胆な試みと見るか、あるいは人民大衆が『官僚主義者階級』を打ち倒す政治大革命と見るかがキーポイントなのである」。
崔之元はここで毛沢東が「官僚主義者階級」という新たな認識を示しながら再び「走資派」という古い言葉に戻ったことを言っているのだろう。だが毛沢東の「官僚主義」批判、共産主義建設論には大衆の自立という意味での民主の復権は含まれていなかった。「文革綱領」(「十六条」)が「群集自己解放自己」、「群集自己教育自己」と言う魅惑的な言葉を含んでいたにしてもである。
それに毛沢東思想が新たな「言語構造」を作り出すに至らなかったと言うが、文革は「文革言語」さらには「大批判」言語という独自な「言語構造」を新たに生み出したとも言えるのであり、そこには文革のはらんだ「解放性」とその転化形態、堕落形態としての邪悪な抑圧性が十二分に示されたのである。
崔之元、粛喜東らにとって「走資派」規定は古い認識(「階級闘争理論」)の残滓であって、彼らはそれを中国共産党マルクス主義のスターリン主義的性格、その政治的他者の見方における根本的な問題性とは見なしてはいない。
彼らが毛沢東や文革での「誤り」について「失誤」という表現を使っていることに注目しよう。普通「誤り」の中国語は「錯誤」という字を用い、それが政治的誤りあるいは路線的誤りを意味する場合には厳しい批判と自己批判の対象となり、ときには政治生命に関わるものとなる。だが「失誤」は基本的には正しい立場に立った上での部分的誤りというニュアンスのものであり、「新左派」にとって毛沢東の「誤り」はそういうものと見なされているわけである。
だが文革において起こった政治と言語の堕落の重要な原因の一つはまさにこの異なる意見や異論の持ち主を敵階級のものと見ることにあった。この見方は本来のマルクス主義さらにはレーニン主義にもなかったものであり、それはレーニン死後の厳しい党内闘争の中で形づくられ、三〇年代の大粛清のなかで完成した姿を取るに至ったスターリン主義政治思想の特性の一つであった。中国共産党は当初からこのスターリン主義の特徴的な政治他者観を引き継いでおり、毛沢東もまたそれを強烈に引き継いでいる。
そしてそれが中国共産党の誇る「整風」、「思想改造」と結びついたとき、その打撃力は恐るべきものとなった。つまりそこでは「誤り」や異論は政治的なものにとどまらず、倫理的、人格的なものと見なされ、したがって「自己批判」もまた政治的な次元のものではなく、批判者への自己解体的一体化以外は容認されることはなかった。
(3)世界的な革命情勢の後退――文革敗退のもう一つの原因
文革の盛衰を当時の国際的な階級闘争の中で捉える必要があると強調しているのが粛喜東である。
「一度は『中国コミューン』という最高の理想へと突撃した文革大衆運動がなぜ急進的な高潮から後退したのかを理解しようとすれば、第二次大戦後の東西の社会主義と資本主義との抗争の中での新中国の特殊な位置、六〇年代に入ってからの全世界的な反体制運動の高潮、および全世界的な革命運動の交錯と不均衡な発展を理解しなければならない」。(「文革を取りまく世界と歴史的時期――文革大衆運動の発展、終結の別の原因」)
粛喜東は一九六〇年代後半の一時期をいわば「戦後第二の革命期」と見なしており、「パリ五月」を始めとするヨーロッパ諸国、東欧、アメリカ、東南アジア、日本、等々でのこの時期の運動を列挙している。
「文革中のパリ・コミューン式の斬新な新社会を建立しようとする社会的思潮と大衆運動の波の高まり、そして欧米での反体制運動の激動と高まりは、一九六七年から一九六八年にかけて同時にその頂点に達していた」。
「欧米諸国での反体制運動が資本主義内部に震動を生み出し、堡塁の内部から資本主義の核心部分が瓦解する可能性がある状況は、文革の大民主にきわめて大きな活動空間を提供した。六〇年代の末になって欧米の反体制運動の退潮が始まり、中国の文革のこの空間は次第に閉ざされた」。
以上の把握との関連でわれわれの関心を強く惹くのは「七・三布告」についての粛喜東のとらえ方である。「七・三布告」とは一九六八年七月、中国共産党が公布した「広西問題に関する布告」のことであり、そこでは中央の命令に反して「武闘」を続ける者は「反革命」として鎮圧すると明言されており、これによって文革造反派運動が事実上解体に追い込まれた重要な文書であり、文革の画期となったものである。
毛沢東がなぜこの布告を出したかについては、従来、毛沢東の文革路線から左にはみ出した部分への弾圧と理解されてきた。その側面は否定できないと思われるのだが、粛喜東の文章の功績はそれを「戦争が革命を阻止」した例として取り上げ論証した点にあった。
つまりベトナム戦争の激化が文革大民主を後退させたと言うのである。粛喜東の「戦後第二の革命期」の把握がどの程度の深みがあったかはさておき、文革の崩壊は「四人組」がでたらめな事をやって人望を失ったのだという「文革徹底否定」論の大キャンペーンにわれわれにしても多かれ少なかれ影響されてきた経過を経てきた今日、その主張はあらためてわれわれの文革の見方を啓発する意義を持つと言えよう。
4.文革再評価と中国ナショナリズム
ところで先にこれら「新左派」たちによる文革再評価がインターナショナルな立場に立っての革命の復権ということではなく多分に中国ナショナリズムに傾斜する傾向を帯びていることにふれた。これらはどういう文脈になっているのか。
その一つは「新左派」の主張が中国国内での「不公正」の問題と共に国際的な「不公正」への抗議をベクトルにしていることに関連している。「社会的平等と社会的公正は国内的平等を含みもすれば国際的平等をも含む」(汪暉)ものだからである。
もう一つは彼らの「自由主義」批判の重要な柱の一つとして、「自由主義」が依拠する西欧民主主義そのものの評価の問題があり、 「新左派」はそれに対抗しうるものとして文革での「大民主」を高く評価し、多党制を批判している。
つまり「新左派」による文革再評価は西欧民主主義に対する「中国の特色ある」政治的、経済的制度の見直しという文脈の中で主張され、それによって当局に黙認されているという側面を持っていると見るべきなのか。
彼らが中国共産党政権を直接批判することなく、また「経済文革」の主張にとどまることもその結果である。
4.「自由主義」派の批判
さて以上のような「新左派」の文革の見方は中国社会の公的世論を形成している「文革被害者」たちの驚きと憤激を呼び起こすと共に、長きに亘って「文革徹底否定」論と鄧小平の「不争論」(論争をするな)のもとに封じ込められてきた文革への種々の思いを解禁することにもなった。
だがそれは「自由主義」にとっては容認できることではなかった。その主要なイデオローグたちの多くが元造反派紅衛兵であり、一九六八年以降の毛沢東による弾圧のもとで、多くの模索を通してついに毛沢東の思想と言語を対象化しつつその圏域から脱してきた彼らにとって、今になっての「新左派」たちの文革再評価はそれでは自分らの苦闘は何だったのかということになるからである。
そしてそれは文革の総括の仕方にとどまらず、「自由主義」にとって「新左派」の「政治民主」、「経済民主」の主張は、中国の将来展望にとって有害なものであった。現在の市場化の先に、今日の中国共産党の専制ではない政治的自由の道を、文革や天安門事件のような「急進主義」的方式ではない形で実現しようというのが「自由主義」の展望だったからである。当然彼らは厳しい批判をおこなっている。
「新左派の致命的な欠陥は実際から離れ、自分が先に設定した結論に達するため、自分が学んだばかりのヨーロッパの最新の学説を披瀝するため、中国の歴史と現実を歪曲し、ばらばらにして自らの理論的枠組みに無理に取り込んでいることである。甘陽と崔之元は九〇年代の初め、中国知識界の主流がヨーロッパの経験を妄信する制度フェティシズムに陥っていると非難した。彼らはヨーロッパの最新の学問と大躍進、人民公社、文化大革命から発掘した制度創新的要素を大いに発揚すればすぐさまヨーロッパのモダニティーを超越できると考えた。だが彼らの高論を中国の現実と比較するとき、それは人に泣くに泣けず笑うに笑えぬ思いを抱かせるだけだった」。(徐友漁「中国九〇年代の新左派を評す」)
これに対して「新左派」はこう反論する。
「このような解釈はたちまち相手を攻めきれず自分で破産した。なぜなら九七年以降、長く大陸に住んで中国の国情を知り尽くしている多くの人たちが新左派となったからである」。(甘陽「中国自由左派の由来」)
だが「自由主義」が「新左派」の提起に対して十分に反批判できているわけではない。それは「新左派」の文革論議が「自由主義」から見るといかに皮相なものに見えても、それが汪暉に代表される「モダニティーの超克」というダイナミックな構図の中に位置づけられ、そのとらえ返しが主張されるとき、それは一つの展望であるかの如き喚起力を持ってしまうからである。
文芸評論家の李揚はこう書いている。
「『新左派』は九〇年代の市場経済の進行のなかで出現した問題に対抗して、『鞍鋼憲法』あるいは『文革』を参考にした建議を提起したのだが、これを自由主義者は心底から憎悪した。だが注意すべきは、彼らは往々にして感情的な記憶の角度から『新左派』の建議を排斥したのであり、決して具体的な学問的な回答ではなかった」。(「『悪魔化』された学術論争」)
1.「新左派」文革論の水準――理論以前の事実認識の誤り
「新左派」の文革再評価に対して「自由主義」はまず事実認識においてまるで話にならないと言う。
徐友漁:「〔「新左派」の〕高論は理論的に反駁されたが、さらに簡単かつ基本的なことは事実面にあり、肝心なことは彼らが称賛する極左路線の産物は、その性質と作用において彼らが美化したようなものではまったくなかった。たとえば政社合一〔政治行政機構と管理機構が一体〕の人民公社とは人々を、『一平二調』〔均等に分配し資材や人を無償で徴用する方式に隷属させること〕を可能にしたものであった。だが人々が生産手段と土地を支配した後、初めて民主選挙と自治の前提が生まれるのである。『「鞍鋼憲法」』の最大の弊害の一つは、工場の中の規則制度を打ち壊したことであり、技術者の生産管理における有効な機能を取り消したことであった。そして毛沢東の『七、八年たったら文革をまたやる』という言葉は、人がそれを聞いただけで顔色の変わる『階級闘争を大いにやる』、『一切の牛鬼蛇神を一掃せよ』ということである。これらすべてのものはそれが大々的に打ち出されたとき『新生事物』、『偉大な創挙』と称揚されたのである。新左派は決して新たなものを創り出したのではなく、死者の霊魂を呼び覚ましたのであり、こうして民族の傷の痛みに乱暴に触れたのである」。(「九〇年代の社会思潮」)
そしてこのような主張の「新左派」の路線性格は、ヨーロッパの「新左翼」がスターリン主義批判をくぐり社会民主主義に接近しているのに比べ、フランクフルト学派的なヨーロッパ・マルクス主義の影響下にスターリン的「左翼性」を評価するようなものとなってはいないかというのが「自由主義」の見方である。
秦暉:「中国の言葉の文脈における『新左派』の思想は、スターリン的体制と社会民主主義の間にではなく、スターリン的体制と『ヨーロッパマルクス主義』の間に位置するものであり、当然、自由主義的色彩の社会民主主義からの距離はさらに遠いものである。中国『新左派』の一部の人々は改革開放前の旧体制から資源を吸収することを極めて強調し、『人民公社』は経済的民主の模範であり、『文革』は政治的民主の模範である、等々と考えた」。(「現代中国の『主義』と『問題』」)
これに対して「新左派」は「自由主義」の文革の見方は当局の「文革徹底否定」と同じではないかと皮肉っている。
李憲源:「文革の打撃に深い怨恨を抱くあれら中国の威風地を払う権力エリートたちと、同様に文革の打撃に深い恨みを抱く中国の自由主義の思想エリートたちとは天然の政治的同盟関係にあるのだ」。(李憲源「女やもめ、情人、『取り持ちや』および無能者、烏合の衆」)
「自由主義」はそういうことではないのだ、自分らの主張は文革をくぐってきた者たちの切実な総括なのだと言う。
朱学勤:「ここでわれわれはあの時代をくぐってきた者が身に沁みて感じている反省について述べてみたい。自由主義派の世代のなかには文革中・後期での反逆思潮を経てきた者たちが沢山いる。その思潮の基本的特徴はまさに今日の新左派の主張のごときものだったのであり、だからこそ当時の毛沢東のユートピアの熱狂に陥ったのである。スターリン体制の失敗をいかに免れるかについては、韓毓海〔「新左派」の指導的イデオローグの一人〕の文章が披瀝した知的系譜から見れば、まずトロッキーがスターリンを弾劾した『裏切られた革命』とその『永久革命論』、つぎにジラス『新しい階級』、最後に毛沢東晩年の『プロレタリア独裁下の継続革命という偉大な学説』が挙げられている。そしてこれらこそはまさに当時の青年反逆者の世代すべてが探し求めて徹底的に究めた知的系譜であった。この知的系譜上で生きていた者たちには一つの共有点があった。彼らはスターリンの『左翼性』に反対するのではなく、その『右翼性』に反対すること、経済的にはソ連体制よりさらに左翼的に『生産手段の所有制を改造』し、政治的にはソ連体制よりさらに『広汎』かつ『直接的な』大民主をおこない、それによって社会主義の名誉を挽回することを主張したのである」。(「一九九八年自由主義学理の言説」)
「一九七八年以前には、われわれは閉ざされた環境の中で模索していたので、当時の官僚体制への批判を、これら知的系譜の枠内をぐるぐる巡りながら、曲がりくねった形で表明できただけだった。一九七八年以後、世界的規模での学術思想の情報に接することが可能となり、われわれは国際共産主義運動の内部で左派としての思想材料を探すという狭い範囲から抜け出すことができて、・・・ようやく今日のこのような認識に達したのである。・・・この認識は学校の図書館で学び取ったものではなく、血の通う身体を切り刻む痛みのなかから煮つめられたものでもあった」。
これら「自由主義」の主張には文革をわが身でくぐってきた者たちの迫力があると言えよう。毛沢東が造反派への弾圧に踏み切った一九六七年後半以降、彼らは必死になって自分らの立場を思想的、政治的に再確認しようとして多くの文献を研究し思索している。
湖南省無聯に関する優れた本(『北京と新左翼』時事通信社、1970)を書いたクラウス・メーネルトは楊曦光「中国はどこへ行く?」について、彼らがジラスの『新しい階級』を読んだとは思えないが、分析の仕方は瓜二つだと述べていた。
だが彼らは読んでいた。それどころかそれは彼らに最も大きな影響を与えた本だったという。さらにはマルクス「フランス三部作」、トロッキー『裏切られた革命』、『スターリン』までもが読み込まれている。
だが「新左派」による文革再評価の登場には二つの要因があった。その一つは「文革徹底否定」論の問題であった。それについては朱学勤自身も「今日の新左派思潮の出現は文革を簡単に否定したことの報いであり、懲罰でさえあるのだ」と認めている。
もう一つは「自由主義」が「改革開放」が生み出した社会的現実に有効な対応をイデオロギー的に提起できていないことにあった。徐友漁が現在の中国は汪暉の言う「モダニティーの超克」が課題となっているどころか、資本主義と市場の積極的意義の汲みつくしの先に政治の民主化をふくむ中国の展望が切り開かれるのだと言っても、その資本主義と市場の権力による展開の中から深刻な社会的差別が顕在化してきている今日、それは説得力を欠くからである。
しかしまずは「自由主義」による「新左派」批判の内容を見ておこう。
2.「鞍鋼憲法」の評価について
崔之元の「鞍鋼憲法」の評価について徐友漁は「中国の現実を知る人々をあいた口がふさがらなかった」と述べていたが、その歴史的推移を記したものに高華「鞍鋼憲法の歴史的真実と『政治的正確性』」がある。彼もまた「これらの論述を読んだとき、私はきわめて怪訝に思った。これらの研究者が提起したそういう判断の事実的な基礎が確かであるか否かについて私は大いに疑問を持っている」と言う。
高華は「鞍鋼憲法」提起の歴史的経過をたどりながら、その実態についてこう述べている。
「問題は鞍鋼が採用したこの改革はつまるところ労働者が自発的に望んだものなのか、それとも指導者が強力に引っ張ったものなのかということである・・・事実が証明していることだが、それは毛沢東の主観的理念が強力に導き、促した産物であった」。
職場では「大弁論」がおこなわれ、労働者たちは合理化に向けての何万件もの提案をおこなっている。そして熱気の中で各種手当ての取り消しまで決議されている。
「だが一九五九年に入ってから鞍鋼の生産状況は危機を示し始めた。原材料と電力の供給が厳重に緊張し、鞍鋼の生産は断続的にストップした」。
そして栄養不足による病気が広がり、労働者たちの不平不満話が広がっていく。ここではその原因について深く立ち入ることはできないが、要するに「大躍進」時に中国産業を襲った現象が鞍鋼にも現れたのである。
興味あるのはそのとき鞍鋼の党支部が取った措置である。彼らは「階級分析」をおこない、「大批判」によって労働者の生産意欲を向上させようとしたわけである。生産の後退、職場の労働意欲の衰えを政治的不満分子の陰謀と見て、「積極分子」を動員してそれを暴露し吊るし上げるお決まりのやり方である。
「歴史がわれわれに告げているように、当時の鞍鋼憲法はただ一つのユートピアの未来図でしかなく生活の現実ではなかった。現実の企業制度は当委員会の指導の下にあって、書記が指揮していた」のであり、そこでの「大民主」の崔之元の評価の仕方は「曲解されたユートピアの未来図」でしかなかった。(何家棟「ポスト・モダン派はいかに現代用語を流用しているか――『経済民主』と『文化民主』を評す」)
3.「自由主義」の文革総括の仕方――「大民主」の批判
自らの造反派としての経験とかっての造反派の指導的メンバ―百余人からの聞き取りによって『様々な造反――紅衛兵の精神的素質の形成と変遷』(中文大学出版社、1999)という優れた文革総括を書いた徐友漁は、歴訪の先々で「大民主」がいかに自分らにとって解放であったかという元造反派たちの証言に接している。
だが今日、徐友漁はそれに否定的である。
「私も文革のなかでおこなわれた大民主がある人々に以前彼らを圧迫していた官僚たちに反抗することができる一種の形式と手段を獲得したと思わせたことを認める。だがこの種のものは真の民主とはまったく共通するものはなく、益するものより弊害の方が大きかったと考えている」。(「総括と反思」)
「まことに文革のなかで大衆が実権派に大字報を貼って彼らを暴露し批判することができたということは文革以前にはできなかったことである。だがこれは大量の『党内走資派』を攻撃し打倒するという文革の戦略の一環でしかなかった。『文革』中の大民主とはどんなものだったか? たしかに大衆には指導的幹部を暴露し批判する言論の自由があった。だがそれは『文革』中に定められた基準に照らしてある幹部が「走資派」であるか否かを争論する自由でしかなかった。一般的に言って、この範囲を越えた言論の自由はなかった。『文革』中に公布されたいわゆる『公安六条』がその最も良い例である」。
徐友漁の文革と毛沢東への批判は厳しく、ほぼ全否定である。これらは文革以降彼が積み上げてきた総括作業の今日的到達点である。
「大多数の中国人にとって『文革』はすでに思い出すに忍びない往事となった。だが私と同年齢の多くの者にとって、『文革』はただ痛苦、恐怖、大災禍ではなく、彼らが『文革』について語るとき、彼らが『文革』のときどの党派に属していたかに関わりなく、総じて一種の懐旧の念と喪失感を伴っていた。彼らにとって『文革』は一つの砕かれた夢であり、彼らはこの夢に自らの理想、情熱、追求を託していた。彼らにとって『文革』は失われたきわめて心地よい栄光の歳月だったのだ」。
「私にしても当然これら一世代の若き日の理想と情熱を抹殺したいとは思ってはおらず、自分自身その中の十分積極的な一員だった者として、彼らを理解し愛惜している。だが私は彼らが主観的なものと客観的なものを区別することを希望する」。
「肝心なことはわれわれの世代は騙されたのだということを承認しなければならないということである。・・・われわれの理想と情熱は弄ばれたのだ」。
「私は『文革』の中で多くの若い学生たちが真心をもって真理を追求したことを承認する。だが多年来の極左イデオロギーの作用によって各種の紅衛兵理論はただ偽りの前提から演繹したものでしかなく、遇羅克らの文章を例外とするのみであった。中国の現代化、民主化の進行過程との関係でいえば、『文革』中の文章と理論は、そこに紅衛兵たちのどんなに多くの思考と探求が凝集されていたにせよ、すべて無価値である。たとえ〔文革〕後期に到って一群の紅衛兵たちが新たな認識を持ったとしても、それもまた『文革』が強いたもの、『文革』への教訓と反思の産物であり、それらの思想の成果を『文革』それ自身に帰すことはできないのである。悪事がときには良い結果を(高い代償を払ってだが)引出すからといって、われわれは良い結果のために悪事を働くことはできないようなものである」。 「自分は弁証法を捨てた」と徐友漁は言う。
以上のような徐友漁の「総括と反思」は「新左派」たちの問題の所在に気づかぬままの文革再評価へ冷水をかけるものとなっている。
だがここには微妙な問題があるように思われる。それは過去の経験の問題点の理論的根拠の認識の仕方なのだが、今日になって見えてきてことから過去を裁断するとき、その過去の清算の仕方が一歩間違えると人がこの現実に関わる実践的・理論的契機、回路の喪失となるという問題である。
たとえば徐友漁は「中国は大きな災禍を代償に毛沢東主義と毛沢東式社会主義への別れを告げる機会を得た」、「文化大革命の災難は人々に毛沢東的社会主義の徹底的な破産を認識させた」と言う。(「社会の変動と政治文化」)
ここには毛沢東の文革理論を部分的「誤り」とか部分的「悪」としてではなく、「誤り」そのもの、「悪」そのものとしてとらえ切り否定し去る意志が示されている。だがここに登場する先にふれた一つの罠、過去を総括する際に陥りやすい陥穽に徐友漁は必ずしも自覚的でないように思われる。
たとえば徐友漁は「全体主義の思想的根源」を解明する作業の一環として、ポパー『開かれた社会とその敵』を取り上げ高く評価している。この本は読み物としてはきわめて面白いものだが、問題はそこでの「理論的根拠」の掘り下げの仕方である。
ポパーはそこでマルクス主義の問題性をヘーゲルからさらにプラトンの弁証法に遡ってその理論構成の中に抑圧的社会の「根拠」を解明しようとしている。だがこういう「思想的根源」の掘り下げの仕方は根本的であるかに見えてどこかに錯誤がある。たとえば思想の型として見れば同一に見える理論も、それが現実化するに際して置かれる諸媒介によって別の性格、機能を帯びる。
たとえばマルクス、レーニン、スターリン、毛沢東からその思想の抑圧的性格、型を抽出してそれを現実的抑圧の「思想的根源」とすることのどこに錯誤がはらまれるかといえば、抽出すれば一見同質のものとなってしまうそれらも、実際には各々のニュアンスやベクトルの差異を持ち、それはそれが置かれる諸条件、諸関係のもとでまったく別の働きをもつものとして現実化する(たとえばそれへの対抗思想や政治的対抗力の有無は大きな作用力を持つ、というように)ことが見落とされているからである。
思想とその現実化の間にそれを媒介する以上のような諸条件、諸関係が果たす作用があるからこそ、人はある思想に対して否定か肯定かの二者択一ではない接し方、評価の仕方(「批判的継承」とか「弁証法的止揚」とか)が可能となるのである。それはそういうとらえ返しも可能ということではなく、どの思想もとらえ返しを可能とする側面を持っているということであろう。
だからこそある局面である積極性を持っいた一つの思想が、何を契機にその堕落、退廃、敗北形態へと転化したかの見きわめが可能となる。
ここでのテーマで言えば、当時の現実の中で「大民主」のはらんだ理論的・実践的な射程力、それが諸関係の中で造反派を鼓舞したことなど無意味とされて「走資派打倒の戦略の一環」に切りつめられ、それが本質だとされてしまうことである。ここからは「大民主」に批判的にであれ、肯定的にであれ総括的に関わる契機は失われ、ただ否定があるだけとなる。すなわち現実への理論的・実践的契機の喪失であり、その空隙はまったく別の新理論(種々の自由主義理論)によって埋められねばならないこととなる。たとえば徐友漁自身、文革のある局面での経験をつぎのように回想している。
「差別、排斥され、打撃を受けてきた学生にとって、一九六六年、『毛主席を筆頭とする党中央』の名で公布された二つの文書は終生忘れがたいものとなった。・・・ほとんどの造反派積極分子がはっきり覚えていることだが、彼らがこの二つの文書の内容を知ったときどれほど感動し喜んだかは、あたかも死刑囚が釈放されたかのようであった。・・・彼らは当時の気持ちを期せずしてつぎのように表現した。『革命方知北京近、造反方覚主席親』(「革命してはじめて北京の近きを知り、造反してはじめて毛主席の親しきを感ず」)」。(『歴史に直面する』中国文聯出版社、2000)
この「二つの文書」とは一九六六年一〇月、毛沢東と中央文革がそれまで曖昧だった文革の闘争対象を明確に「ブルジョア反動路線」に絞ったときの提起であり、それによってそれまで劉少奇、鄧小平主導下の工作組によって弾圧されていた「出身不好」の造反派の復権がなされたのである。
この時期、毛沢東と中央文革の路線はそれが可能性としてはらんでいた「解放性」の頂点に達している。陳伯達のこの講話は劉少奇、鄧小平に連なる驕り高ぶった高幹子弟ら「老紅衛兵」の「血統論」を打ち砕き、江青もまた「血統高貴が何だと言うのだ」と叫んでいる。
「この一時期、毛沢東と中央文革小組はこれら圧迫され、迫害された造反派の盟友であった」。(粛喜東「文革の中での指導者と大衆:言葉、衝突と集団行動」)
それもまた徐友漁が言う「走資派」打倒の「戦略の一環」でしかなかったと見なすことは可能である。だがそれを「悪事がたまたま良い結果を引き出したもの」と見なすことはどこかに錯誤がある。
良きこと(ここでは「解放性」)が純粋に確固として完成した姿で出現するということはないのであり、それは「すぐ目の前にある、与えられ、持ち越されてきた環境のもとで」(マルクス『ブリュメール十八日』)、限界を帯び、諸関係のなかで一歩まちがえればその退廃形態、敗北形態へと容易に転化しかねない脆さをもって登場する。
徐友漁がなすべきだったのは、当時このように造反派を鼓舞した毛沢東と中央文革の路線がどのような問題点を持ち、いかなる文脈の中で否定的なものとなったかの解明であり、今日の到達点からそれを全否定することではなかった。
徐友漁が数少ない例外とする遇羅克は紛れもなく文革のなかで現れた優れた資質を持つ思想家である。その文章には当時隆盛を極めつつあった姚文元らの「大批判」言語とは異質の論理と文体が示されている。
「文化大革命はまさしく彼に文革前の一七年に造反する機会を与えたのであり、文革がなければ彼の『出身論』もなかった。だが他方、遇羅克は紛れもなく文革において重刑を科せられ、のちに銃殺されたのである。このことは文革の両面性を典型的に示している。それは解放的な一面と抑圧的な一面を併せ持っていたのである」。(祝東力)
どこか詭弁のにおいもするこの言い方の中には、しかし文革を見ていくに当たってわれわれが熟思しなければならないある真実もある。
徐友漁も編者の一人である『遇羅克 遺作と回想』(中国文聯出版公司、1999)を見るとき、遇羅克もまた当時のイデオロギー世界と無関係に登場した突然変異だったわけでなく、「出身論」以外の「聯動」(中央文革を公然と批判した老紅衛兵組織)を批判した文章はきわどく中央文革の「走資派」批判の文章に近づいている。
4.「走資派」論の問題
「大民主」の問題性を「走資派」論との関係で分析したのが?小夏「文革と毛沢東の偽の急進主義イデオロギー」である。かって「李一哲」グループに属していた彼女は、天安門事件以後「海外民運派」としてアメリカからの帰国を認められていない。今回「自由主義」としてこの論争に加わっているわけではないが崔之元の文革論文は読んでおり、この文章もその所論の検討から入っている。
彼女はまず崔之元の「毛沢東は正統マルクス主義を超えた」という主張には初歩的な誤りがあると言う。普通、西欧の論者たちが毛沢東の文革思想の新しさと言うとき基準としているのは正統マルクス主義ではなくスターリン主義なのだが、崔之元はその前提的なことを分っていない。
「だから毛沢東の文革思想の評価に当たって問題はこう提起されるべきなのだ。すなわち毛沢東の思想とその文革における実践はスターリン式社会主義の教条性をどれだけ突破したのか? いわゆる毛沢東的な急進的理想主義はスターリン主義からどの程度に急進的理想主義――それがどう理解されたものであれ――の方向へ改良あるいは革新したのか?」
彼女の結論はこうである。
「1、毛沢東はこれまでトロッキーやジラスのように共産党官僚集団を人民を搾取、圧迫する新階級と見なしたことはない。彼の『党内走資派』あるいは『党内ブルジョアジー』についての告発は自由化傾向を持つか、そう嫌疑をかけられた共産党の指導的幹部に対してのものであり、そこには彼の政敵および党内の彼に不満を持つ者たちが含まれていた。
2、毛沢東が文革の中で提唱した『大民主』は政治上の極度の高圧性を前提にしていた。『大民主』のもとで公民としての人身の権利を保護する正規の法制は跡形もなかった。毛沢東および共産党統治に不満を抱いている、あるいは破壊しようとしているとして告発された人は党員であれ非党員であれ大衆組織の容赦ない打撃に晒された。
3、毛沢東の社会改造方案は人民の生活方式と職業上の選択権を根本から剥奪し、軍事化手段をもって社会を組織し、まさに人民全体を党政合一式の国家の全面的支配のもとに置くものであった。
・・・私の見るところ、毛沢東式の文革思想は急進主義的な外観を持っていたとはいえ、本質的にはスターリン主義の復刻版でしかなく、スターリン式の政治的、社会的専制主義のさらに厳しい表現形態とすら言えるものであった」。
このように*小夏は毛沢東の文革と「大民主」についてほぼ全否定している。ここで興味あるのは「走資派」とは毛沢東への異論、その政敵に対しての規定だったとされていることである。ここには「走資派」規定に対するかっての造反派たちによる見方の変化、反省がある。
王希哲はその文革総括(「毛沢東と文化大革命」『中国研究』№123,124、日中出版)で、毛沢東への幻想が砕かれるにつれて「走資派」なる層への見方が変わったと述べていたが、*小夏も同じ見方をしているのかも知れない。
文革終焉後、その代表的な被害者として劉少奇には多くの同情が寄せられてきた。だが少々意外なことに造反派たちの劉少奇への批判は当時のみならず今日なお厳しいものである。
「文革初期の劉少奇、鄧小平のこれらの悪行〔工作組による造反派大弾圧〕について、中国共産党とその御用文人たちは多年に亘ってひた隠しに隠してきた。それはまるで劉少奇、鄧小平が文革中に毛沢東によって粛清され、虐待されたことで、その悪行は都合良く抹消すべきであるかのようであった」。(劉国凱「六六年夏――民衆に向けられた災難」)
「中国共産党系でない非官方人士たちの多くの文革著作においても、往々にして劉少奇の身に起こったことには甚だ多くの同情が寄せられるのに、数多くの第二次『反右』の犠牲者には関心を抱かず無視し一言も触れることがない。このような貴族と平民に対する二重の標準が今なお通用しているのは思っただけでも人の心を寒むからしむることである」。
「劉少奇が責任を負うべきことは実は非常に多いのである」。
劉少奇が国家主席という権力階層にあって人々の運命を左右できる立場にあったことを考えるとき、単に毛沢東への異論の持ち主だったと見るのは妥当か、毛沢東の劉少奇「走資派」規定はただ誤りだったかという問題はトロッキー以来のスターリン主義官僚規定の問題としてそれとしてあるわけだが、毛沢東のそれが階級分析に裏打ちされないスターリン主義的他者批判の一つの典型であったことは否定できない。
ところで以上の「大民主」と「走資派」論の問題をわれわれ自身の運動経験との関係でとらえ返せば何が見えてくるのか。
「四大」が自由な日本のわれわれにとって「大民主」の意義を実感として感じ取るのは難しい。だがわれわれもまた一九六〇年代から七〇年代にかけて一たびは獲得した「大民主」をその意義をつかめないまま、粗略に扱い、乱費し、とどのつまりは失ったのだと認識すべきなのである。どういう意味か。
「大民主」の意義をスターリン主義との関係でとらえ返せばわれわれにとっても分らないことではない。日本共産党のかってのイデオロギー支配の呪縛力は今ではピンとこないが、それを打ち破って以降、党派間対立の「内ゲバ」的堕落、退廃に至る一時期全体に亘って新左翼運動はいわば「大民主」を手中にしたわけである。
だが当時その固有の意義は理解されていない。それはあくまで革命にとっての手段と見なされていたのであり、その限りにおいて党派的利害が優先されるのは不可避だった。だがこの言い方は正確ではない。運動が一たび発展するや党派的に避けがたく分岐し、その間の対立と共同が展開されていくのは、各派が党派利害に固執したからということではなく、それが現実的基礎を持つ大衆運動の場合不可避な過程なのである。
警戒すべきなのはこの分岐なのではなく、むしろこの分岐が強いる緊張に耐え得ず、それは本来あるべきことではないとして理論的、物理的に抑圧する動きであり、それらこそ共産主義の名において開かれた政治空間を抹殺しようとするものである。
と言うのも、将来の共産主義においては民主主義もまた死滅する、そこでは政治的異論などなくなる、すなわち政治的他者問題そのものが消え失せるのだというのがレーニン「プロレタリア民主主義」論の眼目なのであり、新左翼もそれに何の疑いを持つことなく、マルクス共産主義論もそう読み込まれてきたからである。
つまりそれは党派的利害を優先したなどということよりもっと根は深いのであり、自分らの「将来の共産主義社会」論そのものによって日本のこの「大民主」の意義、その維持、防衛、発展など理解できなかったのである。
「内ゲバ」――それは革命運動における政治的他者問題という避けがたく普遍的な問題の特殊形態、敗北形態、堕落形態なのだが――もまた「将来の共産主義社会」の名の下になされたものである以上、その総括は「異論や党派間対立、民主主義そのものが死滅する将来社会」論そのものに及ばなければならない筈である。
「走資派」問題とはまさしくこの政治的異論、政治的他者の問題である。この問題が厄介なのは、政治の場では意見の違いがただ意見の違いとして向き合うのではなく、そこに階級間の問題、支配と被支配の問題が絡まることをめぐっていた。さらにそこには意見とその物質的基礎というマルクス主義のイデオロギー論が関与する。こうして異論=敵性のもの、そうでなくとも「主観的にはともあれ、客観的には」という論理が一つの鋭さであるかのように不可避に登場する。
必要なことは将来社会においては意見の違いそのものが消滅する、そこは「物の管理」をめぐる「統制と計算の単純な作業」(レーニン)の世界だなどという認識は誤りなのだということをはっきりさせることであろう。
5.「告別革命」論の問題
以上のように「自由主義」の文革総括は「新左派」の甘さを突き崩す迫力を持ちえている。彼らの文革と毛沢東批判は部分的な批判にとどまることなくその理論的、思想的根拠そのものを抉り出そうとしている。朱学勤はこの問題を中国近代史に中に探ろうとして、中国革命の原動力となった「民衆主義」(「民粋主義」)、「民族主義」の二つそのものが問題だったと言う。(「五四以来の二つの精神的『病巣』」)
だがここには先にふれたように難しい問題、陥りやすい一つの罠があった。こうして「革命」そのものがこれまでの神聖さを剥ぎ取られ、問題的なものとなる。
李沢厚、劉再復『告別革命――二〇世紀中国を振り返って』(天地図書、1995)はそうした雰囲気の中で出版されている。両派に属しているわけではない李沢厚はこう言う。
「七〇年代末から、私は何度も述べてきたのだが、国内や国外での影響の大きかった革命について、フランス革命を含めてロシア革命、辛亥革命等々をあらためて再認識、研究、分析、評価をすべきであり、革命方式の弊害、それが社会にもたらす各種の破壊を理性的に分析し、諒解する必要がある」。
「私自身は文革後の反革命的気分の代表である」という楊曦光もまた、長期投獄の中での研究と思索、中国の現実の分析の結論だとして「革命」についてつぎのように述べている。
「私には二つの基本的観点がある。その一つは革命という方法によって専制を打ち倒すことはできない。二つは革命は民主化の過程を繰り延べてしまう。さらに言えば、現代の条件下ではもし国と国との戦争がなければ、上層階級内部の大規模な衝突や代理人間の戦争的な局面がなければ、革命という手段によって一つの専制政体を打ち倒すことに成功する確率はほぼ零に等しい。言い換えれば私は革命を主張しない。なぜならまさに一九四九年の革命が中国民主化の過程を数世代にわたって遅らせてしまい、ロシア革命がソ連の民主化を挫折させたように、革命は民主化の過程にとって無益だからである。したがって革命を阻止することが今日の中国の改革にとって十分に重大な現実的意義を持っているのだ」。 (「革命と反革命およびその他」)
これが一つの歴史的な革命のあとに必ず生み出される「反革命」の情緒、心性、イデオロギー、思想なのか、それとも「戦争と革命の時代二〇世紀」を経て成熟した政治的思惟、智慧なのかは「自由主義」、「新左派」双方の内部でも論議があるようである。そしてそれは他人事ではないわれわれ自身の考察課題でもある。
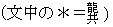
2003・4・10
